みなさん、就職する病院を決めるのに譲れない条件はなんですか?私も大学4年の就職活動ではとても悩みました。今回は何を元に病院を決めると良いのかを私の経験を元にお話します。少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。
就職する病院を決めるポイント
ポイントは下記の5つあります。この5つを総合的に判断してみて下さい。すると自分がここは譲れないなと思う条件もでてくるかもしれません。
下記の5つについて具体的に説明していきます。
- 給料
- 休みの日数
- 家からの通勤距離
- 人間関係
- 急性期か回復期か
給料
結論、給料だけで言えば市民病院やJA厚生連など、公務員扱いとなる公的機関が運営する病院が一番良いと言われています。
ただ、その会社の平均残業時間や手当によって月収も変わるため、入職する前に具体的な数字で年収を比較するのは難しいかもしれません。
理学・作業療法士の具体的な給料が気になる方は下記の記事もどうぞ
休みの日数
まず、就職したい病院が完全週休二日制なのか週休二日制なのかを確認して下さい。
- 完全週休二日制:毎週必ず2日の休みがもらえる
- 週休二日制:1カ月の中で最低1度は週2日の休みがもらえる
完全週休二日制であれば、土日祝合わせての約120日+有給+企業独自の休み(夏季休暇や三ヶ日等)
=年間の休日数となります。
週休二日制では週に必ず2日休みがあるわけではないため、どれくらいの頻度で土曜日出勤(週6日出勤)があるのか、見学に行った際などに確認しておきましょう。
有給の日数は、始めの数年は公務員かそうでないかで差がつきます。公務員扱いとなる公的機関が運営する病院では、1年目から上限の20日がもらえるのに対して、それ以外の病院では1年目では10~12日支給され、その後に1年毎に日数が増えていき、5~10年後に20日になります。
家からの通勤距離
アメリカの研究で通勤時間が長いほど幸福度が低く、ストレスが溜まり怒りやすくなる1)ことが言われています。また、通勤時間が長いほど、運動不足になり、肥満や高血圧を起こしやすい2)とも言われています。
そのため、あまり長い通勤時間は身体によくありません。ただ、私は片道約1時間の電車通勤ですが、その通勤時間が勉強ややるべきことを集中してできる時間になっているため、ストレスはさほど溜まっていない気がします。
人間関係
人間関係はどの仕事をする上でも、1番重要と言って過言ではないと思います。
ただ、これは入職してみないと分からないことでもあるため、一概に何が良いということは言えないのかもしれません。
ただ!!パワハラが酷いという噂のある人がいないかどうかだけ確認しておくと良いです!
自分が就職を考えている病院へ実習に行った同級生や先輩に聞きましょう!
急性期と回復期の違い
就職してみて気づいた、急性期と回復期の違いを、私の中での違いをまとめました
- 急性期:病態が安定しておらず急変の可能性があるため、リスク管理をしっかりとした上で・その日の体調に合わせて歩行や筋力トレーニングを実施する。 担当する患者人数は多く、大抵は1カ月以内に退院される。
- 回復期:病態が安定しているため、リスク管理よりも関節可動域(ROM)や徒手筋力検査(MMT)などの身体機能評価を十分に行った上で歩行訓練や筋力トレーニングを実施する。担当する患者人数は少なく、退院までも2カ月以上と長いことが多い。
急性期と回復期では就職後に求められる知識が違うため、勉強すべき内容や分野が異なります。この二つはどちらが良いというわけではありませんが、自分がどちらに合うかを実習で決められると良いです。病院によっては、急性期・回復期・維持期・老人保健施設などをローテーションで移動することがあるため、経験という観点では移動がある病院がおすすめです。
まとめ
いかがでしたか。就職活動は正直、縁だと思います。
自分の成績だけでなく大学の先生や先輩からの情報もとても大事です。
皆さんが無事就職できるように応援しております!
参考文献
1)Stutzer, A., & Frey, B. S. (2008). Commuting and life satisfaction in Germany. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 8(1).
2)Hoehner, C. M., Barlow, C. E., Allen, P., & Schootman, M. (2012). Commuting distance, cardiorespiratory fitness, and metabolic risk. American Journal of Preventive Medicine, 42(6), 571–578.
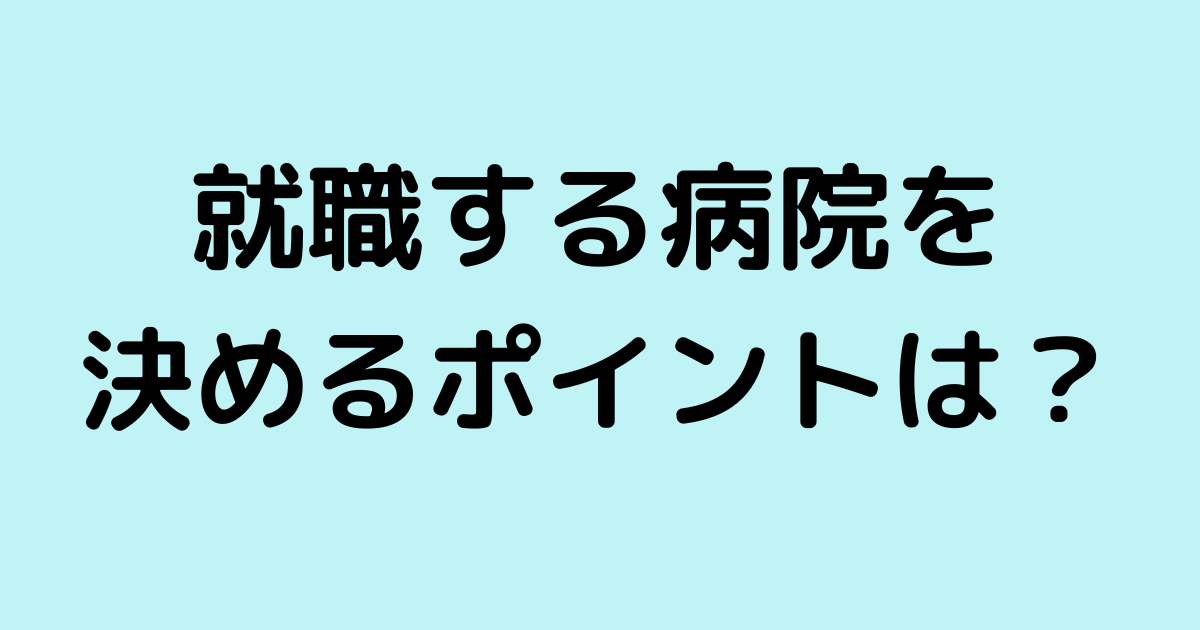

コメント